インタビュー
ベテラン看護師が選んだ、「医療と看護の橋渡し」となる新たなキャリアパス【診療看護師インタビュー】
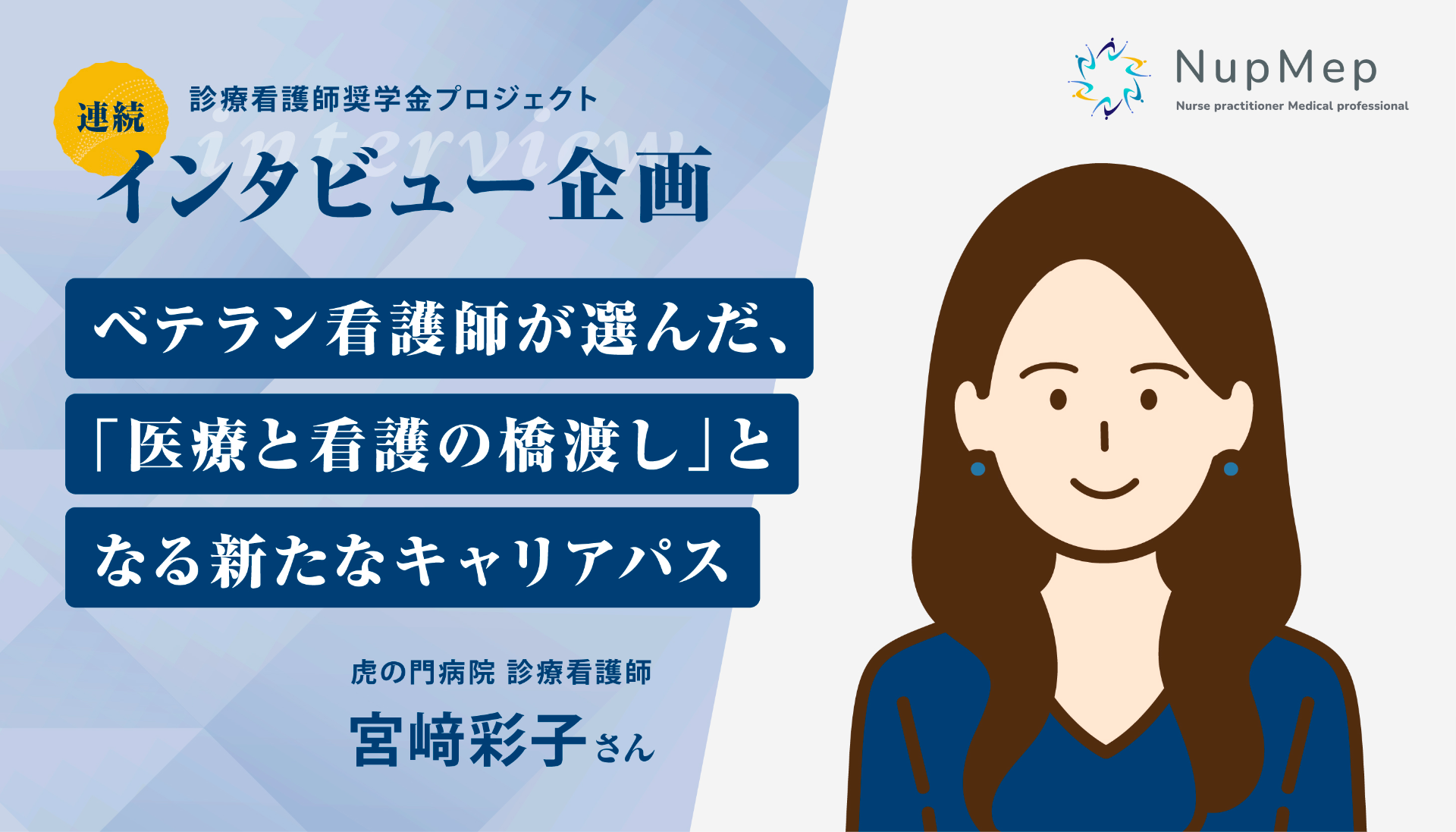
一般財団法人診療看護師等医療従事者支援協会(通称:NupMep)が挑戦するクラウドファンディング「診療看護師奨学金プロジェクト」の期間中に、連続インタビュー企画を開催しています。
クラウドファンディング「診療看護師奨学金プロジェクト」とは
診療看護師を目指す看護師へ返済不要奨学金を提供するためのクラウドファンディングを、2024年12月11日から2025年2月11日まで実施しています。
第3弾は、20年以上のキャリアを持つ看護師から、診療看護師となった宮﨑さんにインタビューさせていただきました。
診療看護師1年目の宮﨑さんに、豊富な経験、診療看護師を選んだ理由、日本における診療看護師の役割などについて語っていただきました。
インタビューさせていただいた方
宮﨑 彩子 さん
虎の門病院 勤務
インタビュアー
山下 実和
一般財団法人 診療看護師等医療従事者育成支援協会
クラウドファンディング担当
看護師として積み重ねてきた20年と、変化を恐れないキャリア選択
山下:まず、宮﨑さんの看護師としてのキャリアについてお聞かせください。
宮﨑さん:これまで3つの病院で、看護師としての経験を合計20年以上積んできました。最初の病院では16年以上勤務し、主に集中治療領域の病棟(主にHCUやCCU)で働いていました。基本的に、患者さんにとって良いと言われていることを積極的に取り入れていきたいという思いで仕事をしてきました。
山下: 最初の病院を離れられた理由はなんですか?
宮﨑さん:集中治療に対して、より専門的に関わりたいと考えたんです。集中治療室(ICU)には『オープン』と『クローズド』という2つのタイプがあります。オープンICUでは各診療科の医師が主導で治療を行いますが、クローズドICUでは集中治療の専門医が全体を管理します。より集中医療に長けた先生のアプローチ方法を学びたいと思い、クローズドICUのある病院に移りました。
山下: その後、3つ目の病院では新設の立ち上げに関わられたそうですね。
宮﨑さん:はい。伝統のある病院では、1つのルールを変えるのに大きな労力が必要なんです。新しい病院なら、エビデンスに基づいて、より良い方法を柔軟に選択できる。それが魅力でした。例えば、せん妄の評価スケールのひとつをとっても、どのスケールを使うか、スタッフ全員で一から議論できました。みんな経験を積んできた環境が違うので、それぞれの知見を持ち寄って、最適な方法を選べる。とても大変でしたが、その分自分のキャリアにおいて刺激的な体験でした。
より広い視野を求め、診療看護師という選択へ
山下: 3つの病院での経験を経て、診療看護師を目指そうと思われた経緯を教えていただけますか?
宮﨑さん:3つ目の病院で働く中で、次のステップを考え始めたんです。集中治療の分野で様々な経験を重ねてきて、オープンICUとクローズドICUの両方を経験し、新設病院で1からルールを固めていくことにも関わりました。でも、このまま病院を変えても、看護師としてできることには限界があるなと感じ始めたんです。
山下: その時、スペシャリストとしての道を考えられたのですね。
宮﨑さん:そうですね。看護師として10年目を過ぎた頃から、認定看護師や専門看護師への道も考えていました。周りからも『なぜ資格を取らないの?』とよく言われました。ですが当時、私の周囲にいた認定看護師の方達の活動がとても積極的で、自分にはできないなと感じて、実際に行動に移せませんでしたね。
そして、看護師として20年経って認定看護師や専門看護師を選択しなかったのは、それらの資格は看護師の領域の中での活動になるため、自分の中でうすうす感じていた看護師の限界を超えることはできないと考えていたからです。
山下: 具体的にどのような限界を感じておられたのでしょうか?
宮﨑さん:患者さんのことを理解していても、看護師の立場では説明できない部分が多くありました。例えば、治療方針や検査結果について、理解はしていても『それについては医師から説明があります』という形になってしまう。患者さんとの信頼関係ができているのに、重要な説明ができないというもどかしさがありました。この壁を超えるには、医療の視点も必要だと感じていました。
山下: その中で、診療看護師という選択肢に出会われたわけですね。
宮﨑さん:はい。診療看護師について知った時、『これだ』と直感的に思いました。面白いことに、これまで認定看護師や専門看護師になることを迷っていたときとは違い、すぐに行動を起こしていました。どこの学校があるのか、どういうカリキュラムなのか、必要な要件は何か、すぐに調べ始めましたね。それまでの私からは考えられないくらい、行動が早かったです。
診療看護師を目指す上での、経済的負担と情報不足
山下: 診療看護師資格取得のために就学されていた大学院での2年間について、特に経済面での課題を教えていただけますか?
宮﨑さん:私の場合は完全に看護師を辞めて、大学院に進学しました。2年間は収入がない状態で、貯金を切り崩して学費と生活費を賄いました。私の同期では、4分の1が私のように完全に仕事を辞めて入学し、4分の3が病院からの何らかのサポートを受けていたように思います。
山下: 病院からのサポート体制もあるのですね。どのようなサポートなのでしょうか?
宮﨑さん:病院によって支援内容は本当に様々です。基本給しか出ないところ、基本給の8割出るところ、基本給に加えて交通費も出るところ、さらに宿泊費までサポートしてくれるところなど、病院によって全然違います。また、サポートを受ける場合は、卒業後にその病院へ戻ることが条件となるケースが多いようです。
山下: 地方からの進学者も多いとお聞きしましたが、いかがでしょうか。
宮﨑さん:そうですね。私の同期の場合、東京出身者は4分の1程度で、多くが地方からの進学者でした。地方から来る場合、学費に加えて家賃や交通費などの負担も大きくなります。特に既に結婚されている方の場合、家族は地元で暮らし続け、単身で上京して進学するケースも多く、二重生活での経済的負担は相当なものです。
山下: 情報面での課題もあるとお聞きしました。
宮﨑さん:はい、診療看護師に関する情報へのアクセス手段が、学校によって本当に限られているように思います。例えば、就職活動の際、募集している病院を見つけること自体が大変でした。学校によって就職支援の体制も違いますし、他大学の情報なども入ってこない。また、利用可能な奨学金制度などの情報も、自分で探さないと全然わからないのが現状です。
山下: 学びの面では、どのような課題を感じていますか?
宮﨑さん:医師が6年かけて学ぶ内容の一部を2年間で学ぶと言っても過言ではないので、とても大変です。臨床経験の豊富な看護師とはいえ、医学的な知識や技術については、まだまだ学ぶべきことが多いと実感しています。自分の中でも『大学院に2年行ったからといって、医師が学んだ6年間にはとても及ばない』という認識は常にあります。だからこそ、診療看護師として就職した後も、継続的な学習が必要だと感じています。
医療と看護の架け橋としての「診療看護師」
山下:現在の診療看護師としての業務内容について教えていただけますか?
宮﨑さん:私は診療看護師1年目なので、現在はローテーション研修の最中で、循環器内科の先生たちと一緒に働いています。私の病院では、2年間の研修期間があり、数ヶ月ごとに診療科を変えていく予定です。現状は半年単位でのローテーションになっていますが、来年は2,3ヶ月ごとに色々な科を回る形になる予定です。
山下: 具体的な業務内容はどのようなものでしょうか?
宮﨑さん:複数の医師とチームを組んで診療に当たります。医師と一緒に診察を行い、検査や点滴、内服のオーダーなどを代行入力したり、コメディカルと情報共有を行います。
山下: 以前の看護師業務とは大きく異なるのでしょうか?
宮﨑さん:はい、異なります。以前は体を拭くなどの直接的なケアを行う立場でしたが、今はそれをオーダーする側になりました。看護師時代の経験は貴重で、それを活かしながら医療の視点も加えて患者さんを診ようと心掛けています。
山下: 診療看護師の特徴的な点は何でしょうか?
宮﨑さん:病棟ではなく診療科に属することにより、ICUから一般病棟まで、患者さんの状態が変化しても継続的なケアができることが特徴です。一般の看護師は病棟に紐づいた配属になるため、例えばICUの看護師は一般病棟では患者さんを診ることができません。診療看護師であれば、重症期から回復期まで、継続して患者さんに関わることができるんです。
山下: その継続性は、具体的にどのような利点につながりますか?
宮﨑さん:患者さんの全体像を把握できることが大きいですね。例えば、がん患者さんの場合、診断を受けた時から治療中の状態変化、そして回復期までの過程で、患者さんの思いや考えの変化を理解することができます。過去の経過を知っているからこそ、現在の状態により適切に対応できますし、病棟看護師や医師とも、患者さんの情報を共有しやすくなります。
山下:配属先によって、診療看護師の役割は異なるのでしょうか?
宮﨑さん:はい、病院や診療科によって求められる役割は大きく異なります。患者数が少ない診療科では、担当は持たずに全体を見回って必要な対応をする場合もありますし、手術やカテーテル検査に特化して入る場合もあります。まだ診療看護師という職種自体が発展途上で、それぞれの環境に応じて柔軟に対応していく必要があると考えています。
日本の医療における診療看護師の可能性
山下: 日本の医療における診療看護師の可能性について、どのようにお考えですか?
宮﨑さん:診療看護師は、まだ注目されていないけれど確実に必要とされる『隙間産業』的な存在かもしれません。医師の働き方改革が進む中で、医療の質を維持・向上させるためには、私たちのような存在が必要なんだと思っています。医療と看護、両方の視点を持ちながら、患者さんに寄り添える存在として、もっと活躍の場が広がっていくはずです。
山下: 具体的にどのような役割を果たせるとお考えですか?
宮﨑さん:例えば、手術後の患者さんには、リハビリや食事など、生活全般にわたる課題が出てきます。医師は手術に専念し、各専門職がそれぞれの分野を担当しますが、診療看護師は看護師としての経験を活かしながら、患者さんの全体像を見て、各職種をつなぐ役割を果たせます。また、人口減少に伴う医療人材の不足が懸念される中、診療看護師は重要な役割を担えると考えています。
山下: これから診療看護師を目指す人へのメッセージをお願いします。
宮﨑さん:診療看護師の世界はまだまだ発展途上で、私自身も日々手探りで進んでいます。しかし、“なぜ診療看護師になりたいのか”という軸を自分の中に持っていれば、さまざまな局面に直面しても向き合えるはずです。私自身も知識不足に悩みながら、日々、患者さんから得た情報を医師に共有し、治療方針を一緒に模索しています。診療看護師としてリアルタイムで治療に関わることができ、看護師時代とは違うかたちで、患者さんの“今”に寄り添える実感があります。資格を取るために一歩踏み出すことは勇気がいるかもしれませんが、その一歩が未来を大きく広げるきっかけになるかもしれません。迷って考えることも大事ですが、踏み出さなければ何も始まりません。人生は一度きりですから、踏み出してみて、もし合わなければその時にまた別の選択をすればいい。今踏み出すことが、次のステージを切り開く一歩になるのだと思います。
山下:これから診療看護師を目指す方にとって、心強いメッセージになったかと思います。
本日はインタビューさせていただき、ありがとうございました!
宮﨑さん:ありがとうございました!
編集後記
診療看護師という職種は、まだ発展途上の段階にあります。しかし、宮﨑さんとのインタビューを通して、医療と看護の両方の視点を持ち、柔軟に役割を果たせる存在として、これからの日本の医療に大きな可能性をもたらすのではないか、と改めて診療看護師の活躍への期待が高まりました。
また、宮﨑さんからも言及がありましたが、診療看護師が活躍する社会の実現のためには、経済的支援の充実や情報提供体制の整備などが欠かせないことも実感しました。
熱い思いを抱いて、より良い医療の形を追及する宮﨑さんのような診療看護師が、どんどん日本で活躍できるように弊財団も精進していきます。
(インタビュアー山下)
診療看護師奨学金プロジェクトへのご支援をお願いします
※本プロジェクトは、2025年2月11日に終了いたしました。
合計20名の方から、95万円のご寄付をいただきました。
応援くださった皆様、誠にありがとうございました。
NupMepは診療看護師を目指す看護師や学生へ返済不要の奨学金提供を開始するため、クラウドファンディングで600万円を募集するプロジェクトを2025年2月11日まで実施しています。
- 目標金額(1st Goal):600万円
- 募集期間:2024年12月11日(水) 9:00 〜 2025年2月11日(火) 23:59
- 資金使途:診療看護師を目指す看護師・学生への奨学金、診療看護師のコミュニティ運営、事務局運営
皆さまのご支援により、未来の医療を共に支えませんか?
寄付金は全額、奨学金として活用され、診療看護師の育成と医療現場の改善に直結します。
