インタビュー
「あるべき医療の姿とは」日米での入院体験から語る、未来の日本医療に望むこと【患者家族インタビュー】
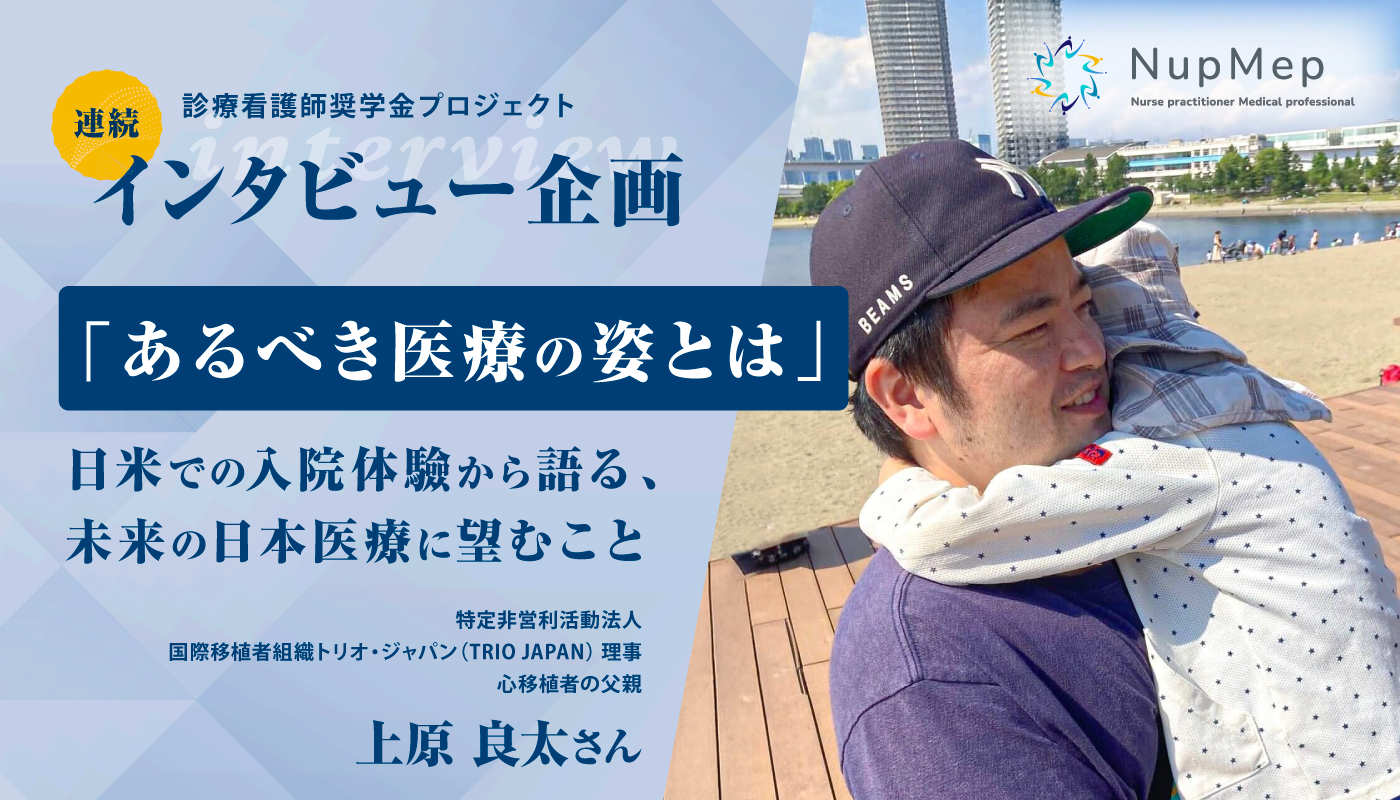
一般財団法人診療看護師等医療従事者支援協会(通称:NupMep)が挑戦するクラウドファンディング「診療看護師奨学金プロジェクト」の期間中に、連続インタビュー企画を開催しています。
ーーー
クラウドファンディング「診療看護師奨学金プロジェクト」とは
診療看護師を目指す看護師へ返済不要奨学金を提供するためのクラウドファンディングを、2024年12月11日から2025年2月11日まで実施しています。
詳しくはこちら:https://congrant.com/project/nupmep/14095
ーーー
日本の医療は世界に誇れる水準を持ちながら、現場では様々な課題を抱えています。
第5弾は、お子様の心臓移植のために日米両国で入院付き添いの経験がある上原さんに、患者のご家族の視点から見た医療現場の実態と、これからの日本医療の可能性についてお話を伺いました。
インタビューさせていただいた方
上原 良太 さん
特定非営利活動法人国際移植者組織トリオ・ジャパン(TRIO JAPAN) 理事
心移植者の父親
インタビュアー
山下 実和
一般財団法人 診療看護師等医療従事者育成支援協会
クラウドファンディング担当
2年半の入院生活から見た日本の医療現場
山下:まず、上原さんのお子様が入院に至った経緯を教えていただけますか?
上原さん:2015年に生まれた下の子が、1歳になる頃に風邪のような症状が続いていました。近くの病院では風邪と言われていたのですが、念のため大きな病院で見てもらったところ、心臓が大きくなっているということで、すぐに大学病院に運ばれました。そこで拡張型心筋症と診断され、最終的には移植しかないという話になり、息子の闘病生活が始まりました。日本で移植を待機していた2年半の間、複数の病院を転院しました。
山下:2年半の治療についてお聞かせください。
上原さん:最初は大学病院のICUで集中的な管理を受けました。その後、内科的な治療を試みるため別の病院に移りました。しかし、内科的な治療も限界となり、補助補助人工心臓「VAD」をつけなければいけないということになりました。それができる病院に転院することになりました。
山下:補助人工心臓を付けてからの生活はいかがでしたか?
上原さん:補助人工心臓を付けると24時間の付き添いが必要になるんです。私と妻と母の3人でローテーションを組んで対応していました。これは本当に大変でした。なぜかというと、日本の病室は24時間付き添いを前提とした環境になっていないんです。寝る場所も十分ではなく、食事の持ち込みも制限され、Wi-Fiもない。シャワーもゆっくり使えない。付き添うことは必要なのに、その環境が整っていないんです。
山下:なぜ24時間の付き添いが必要だったのでしょうか?
上原さん:看護師さんの人数が限られていることは大きな理由の一つだと思います。自分の子ども以外にも、たくさんの患者さんがいる中で、うちの子どもだけに付きっきりで見ることはできないんです。にもかかわらず、補助人工心臓は腹部にホースが付いていて、子どもは小さいのでよく動き回っていました。血液をサラサラにする薬を飲んでいるので、ちょっとしたことで出血のリスクもある。そういったことを常に見ておけるのは、私たち家族しかいなかったんです。
山下:そのような大変な環境で、周りに頼れる他のご家族などはいたのでしょうか?
上原さん:いなかったです、もう本当に手探りでしたね。同じ病気の子どもや、同じ病気の子どもを持つご家族は日本に増えてきていたんですけど、その当時、治療できる病院が限られていました。私の子どもが入院していた病院では、拡張型心筋症の治療をおこない、補助人工心臓のケアを始めた一期目が私の子どもだったという状況でしたから。
山下:そのような状態で、医療者との関係性はいかがでしたか?
上原さん:特に看護師さんたちには本当に感謝しかありません。毎日接しているのは看護師さんで、その場その場で工夫して、患者のことを本当に考えて対応してくれます。
2年半の入院生活で、新人だった看護師さんが成長していく姿も見させていただきました。中には、家族で結婚式へ呼んでいただき、子どもがリングボーイを務めさせてもらうほどの関係になった看護師さんもいます。
山下:看護師さんたちの働く環境についてはどのように感じられましたか?
上原さん:本当に人手が足りていないと感じました。例えば、病棟では色々な機器のアラームが鳴るんですが、看護師さんが少なすぎて対応が追いつかない。でも、これは看護師さん個人の問題ではなく、仕組みの問題のように感じていました。
アメリカの医療現場で体感した快適な環境と分業制
山下:日本での2年半の待機を経て、アメリカでの治療を選択されたそうですが、その経緯を教えていただけますか?
上原さん:日本で2年半移植を待っても、なかなか臓器移植の機会に巡り合えませんでした。そこで、トリオ・ジャパンという団体に相談に行き、海外での移植を目指すことになりました。渡航資金を集めることができ、ニューヨークのコロンビア大学病院に渡航しました。そこで3ヶ月ほど待機して、ようやく移植の機会を得ることができました。そして、2019年に息子は移植を受け、2020年に日本に帰国しました。
山下:アメリカの病院での入院生活はいかがでしたか?
上原さん:まず驚いたのは、家族への対応の違いです。日本では、移植待機していた子どもの兄が病室に入れなかったんですが、アメリカでは病室で家族4人が揃って過ごすことができました。部屋もとても広かったですし、全然家族4人が入れるような病室だったんですね。もちろん一般病棟もそうだし、ICUもすごく広くて。
山下:食事面での違いはありましたか?
上原さん:日本の病院は食事面にとても厳しくて、子どもの食べ物も病院食のみに制限されていました。それもあって、現在偏食気味になってしまいました。小さい頃の食育の観点から、もっといろいろなものを食べさせてあげたかったなと思います。但し、アメリカではそんなことはなくて、いつでも何を食べてもいいし、何を持ってきてもいいし、何を作って来てもいいよと言われていました。食べてまずは元気になることが重要だから、という考え方でした。
山下:医療スタッフの体制に違いはありましたか?
上原さん:ナースプラクティショナー(診療看護師)という白衣を着ている看護師さんがいました。私たちも帰国する直前まで、その人がお医者さんだと思っていたくらいです。頻繁に話を聞いてくれて、薬の処方なども行ってくれました。看護師さんたちが分からないことがあると、ドクターの前にまずナースプラクティショナーが対応するという体制になっていました。
山下:医療スタッフの体制に関して、他に気づいたことはありますか?
上原さん:分業がとても進んでいました。例えば、採血だけを専門に行う人がいて、その人が一日中病棟を回っているんです。日本では入院中はドクターが採血をしていましたが、アメリカではお医者さんが採血するということは一度もありませんでした。
また、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)という専門職の方もたくさんいて、子どもの相手をしてくれたり、大学生のボランティアと連携して子どもと遊んでくれたりしました。その間、親は休んでいてもいいと言ってくれて、大変ありがたかったのを覚えています。
山下:日米の医療を体感されて、どのような違いを感じましたか?
上原さん:日本の医療はクオリティが高いですし、めちゃくちゃ丁寧なんです。一方、アメリカの医療は、雑な部分もありつつ、本当に大事なことは漏らさない。個人的には、そんな印象を受けました。
例えば、日本だと補助人工心臓の脇にチェックリストがあって、機器に埃が被っていないかなどの細かいことまで当時はチェックしていました。アメリカでは機械は埃まみれでしたが、本当に大切な医療行為に集中している、といった具合です。
日本における、より良い医療の実現に向けて
山下:現在は、お子様の心臓移植の経験をもとに、どのような活動をされていますか?
上原さん:自分の子どものことで、たくさんの方々に本当にお世話になりました。そういった経験もあって、トリオ・ジャパンの理事として、移植医療を特別な医療じゃなく、普通の医療にするための啓蒙活動などを通じて、移植医療をもっと日本に広めていきたいと思っています。
山下:今後の日本医療に期待することは何でしょうか?
上原さん:個々の医療者の努力だけでは解決できない課題があります。私としては、役割分担の整理や、患者・家族への環境整備など、システムとして改善できることがたくさんあるのではないかと思っています。医療の本質を見失わず、かつ医療者も患者も無理なく過ごせる環境づくりが必要なのではないでしょうか。
山下:様々な体験からのお話をありがとうございました。上原さんがアメリカで経験した、専門性のある看護師の活躍や分業の促進など、日本医療がよりよくなるためのヒントを沢山いただきました。本日はインタビューさせていただき、ありがとうございました。
上原さん:こちらこそ、ありがとうございました。
編集後記
上原さんの経験から、日本医療の持つ課題と可能性が見えた気がしました。個々の医療者の献身的な努力と高い技術力を持ちながら、システムとしての柔軟性や、患者・家族への環境整備においてまだまだ良くできる伸びしろを実感しました。
そして、ナースプラクティショナーのような専門職の存在も印象的でした。医師と看護師の役割分担を最適化し、より効率的な医療の提供を可能にする可能性を秘めていると思います。より良い医療の未来に向けて、私たちNupMepが診療看護師奨学金プロジェクトをおこなう意義を改めて感じました。
(インタビュアー山下)
診療看護師奨学金プロジェクトへのご支援をお願いします
※こちらのクラウドファンディングは終了しています。多くのご協力・ご支援ありがとうございました。
NupMepは診療看護師を目指す看護師や学生へ返済不要の奨学金提供を開始するため、クラウドファンディングで600万円を募集するプロジェクトを2025年2月11日まで実施しています。
- 目標金額(1st Goal):600万円
- 募集期間:2024年12月11日(水) 9:00 〜 2025年2月11日(火) 23:59
- 資金使途:診療看護師を目指す看護師・学生への奨学金、診療看護師のコミュニティ運営、事務局運営
皆さまのご支援により、未来の医療を共に支えませんか?
寄付金は全額、奨学金として活用され、診療看護師の育成と医療現場の改善に直結します。
